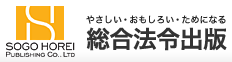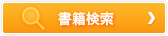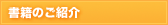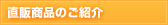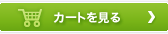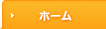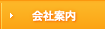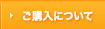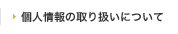■今週の市場展望
著者:青柳孝直
12/16号
『特集:消えた日本の喫茶店文化その後』
- 喫茶とは「茶を飲むこと」(角川国語辞典)、喫茶店とは「飲み物・菓子・軽い食事を飲食させる店」(同前)とある。街中から喫茶店が消え始めたのはいつの頃だったろうか。考えるに1980年代前半あたりからだったと思う。
- 「茶を飲む」とは「コーヒーを飲む」が一般的だった。「お茶する?」とは「コーヒーを飲みに行く?」とほぼ同意語だった。そして喫茶にはタバコが付き物だった。20世紀後半あたりから禁煙ムードが拡大、現在ではあたかも“犯罪のような”扱いをされるようになった。その禁煙ムードも喫茶店を消滅させる大きな要因のように思う。
- 概念論はともかく、街中の喫茶店を(実質的に)駆逐したのはセルフサービスのカフェが根付いたからだった。先鞭を切ったのはドトール。1983年にスタートしたドトールの形式は徐々に拡大、マクドナルドやスターバックスが後を追う格好となった。
- 喫茶店のコーヒーはラーメンの値段とほぼ同じだったと思う。自分の学生時代、ラーメンは確か120円前後。コーヒーの値段もそのレベルだった。1980年代はその値段が500円前後に上昇していた。殴り込みをかけたドトールはコーヒー一杯を200円前後で販売した。ただひたすらコーヒーを飲みたい者は、その安さに流れていった。
- たばこの歴史も同様だった。喫煙が当たり前だった1970年代から、セルフサービスのカフェでは分煙となり、ついには店内全面禁煙となった。今ではタバコを吸うなら屋外へどうぞというスタイル。NYでは屋外での喫煙もNOのサインを出している。
- こうした「安さ」が売りのコンビニ・カフェの流れを変えたのはスターバックスだった。客単価を600円前後と少々高めに設定、コーヒー類の品質の高さと、ゆったりした内装、無線LAN環境を備えた「居心地のよさ」も“売り”にした。新鮮だった。
- かくしてスターバックスは、自宅でも学校・職場でもない、そして一流ホテルにもない「(カジュアルな)居場所」を提供することで消費者の支持を得て日本全国を席捲、スタバと呼ばれるようになり、日本独特の文化とまで言われるようになっていった。
-
自分の場合、コーヒーはアイスコーヒ一本槍。「夏でも冬でも、アイスコーヒ」である。ただ日本以外ではアイスコーヒーは飲めない。一見英語に見える「アイスコーヒ」は実は日本の造語である。シアトルを本社とするスターバックスは、そのアイスコーヒも日本仕様にしている。違和感がない。根付くはずである。
ただその勝ち組スターバックスにも異変が見える。10月の売上は前年同月比1%減と15カ月振りに減少した。危機感を感じた同社は、店内調理のパンやジュース、酒類も提供することを企画、今年から開始した住宅街中心の高級店で“実験”を開始している。 - セルフサビースカフェ各社は、かつて自らが駆逐していった喫茶店を見直し、更なる進化を図ろうとしている。「(なつかしの)喫茶店」はもはや死語である、残念ながら…
青柳 孝直
(あおやぎ・たかなお)
【略歴】国際金融アナリスト
1948年 富山県生まれ。
1971年 早稲田大学卒業。
世界の金融最前線で活躍。日本におけるギャン理論研究の第一人者との定評を得ている。
著書は、『新版 ギャン理論』『日本国倒産』など多数。翻訳書としては、『世界一わかりやすいプロのように投資する講座』など。
連絡先:
株式会社 青柳孝直事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂2-10-7-603
TEL:03-5573-4858
FAX:03-5573-4857
書籍紹介
-
ISBN:978-4-86280-068-8
定価:1,365円
-
ISBN:4-89346-913-4
定価:2,520円